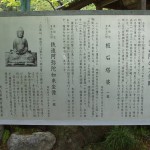2014年5月15日木曜日 雨のち晴れ
先日、大塚本社のASさんから、埼玉県ときがわ町にあります慈光寺の菁莪(しゃが)の写真をもらいましたので記事にしてみます。
このかわいらしくも凛として華やかな花を持つ植物は、菁莪(しゃが)と言います。著莪とも射干とも書きます。アヤメ科の宿根草で胡蝶花と書かれることもあるとか。
ここ慈光寺にはたくさんのシャガが群生しています。
菁莪と書いて「せいが」と読む例は多くみられ、特に明治時代に各地にて学校名として使われていました。今でも小学校や中学校で使われ続けている例もままあります。菁莪とは中国の詩経にある「菁菁者莪」から由来しているようで、「菁菁(盛んに茂るさま)たる莪(あざみ)は材を育するを楽しむ、君子はよく人材を長育す」という文章より、人材を育成すること。英才の育成を楽しむことを「菁莪」という言葉として使われていたようです。そんな「せいが」と「しゃが」の違いについては・・・すみませんわかりませんでした。
さて慈光寺。文化財の宝庫のお寺です。↓こちらは時の鐘。
↓山門と阿弥陀堂です。
↓観音堂です。陣外には伝説の「夜荒らしの名馬」があります。左甚五郎作と伝えられています。夜になるとこっそりと抜け出して付近の田畑を荒らしたという伝説があります。
↓1262年に、亡き畠山重忠・重保親子の供養のために、勝呂左衛門尉行直によっておさめられた板碑(青石塔婆)
↓空海書の破体心経です。
↓こちらは良寛書の楷書心経です。
↓国指定重要文化財の銅鐘です。
慈光寺は奈良時代の開山のお寺で、埼玉県では法灯をともし続けている最古のお寺です。鎌倉時代には関東屈指の大寺院でたくさんの塔頭が立ち並んでいました。ゆえに貴重な文化財を多く蔵しております。
↓国指定重要文化財の慈光寺開山塔です。右の建物は覆い堂で、その中に塔が守られています。
↓釈迦堂跡です。昭和60年(1985年)11月26日、放火により釈迦堂や鐘楼が火災となり、釈迦如来像、蔵王権現像などが焼失してしまったそうです。
↓足元のシャガと新緑の森と、お向かいの山。とてもいい季節です。見えていませんが、お向かいの山との間には都幾川が流れています。
少し移動し、すぐ近くの霊山院に来てみました。↓しまっている門は勅使門です。菊の紋が見えます。
霊山院は、慈光寺の塔頭の一つとして建てられ、東国最古の禅寺。
↓一休さんと木魚とねずみです。
帰り道、慈光寺山門跡の板碑群を見て行こうと思います。
慈光寺は坂東三十三観音の九番霊場になっています。
文化財の宝庫の都幾山慈光寺。菁莪(しゃが)は今が見ごろです。