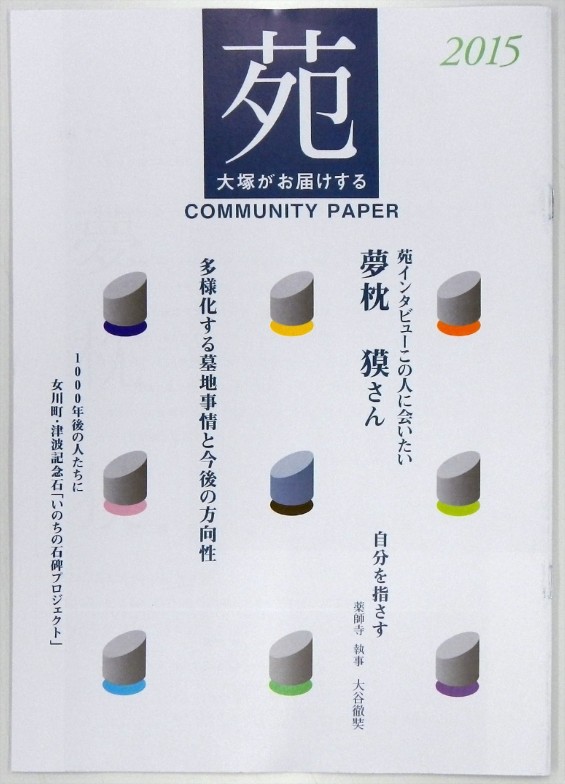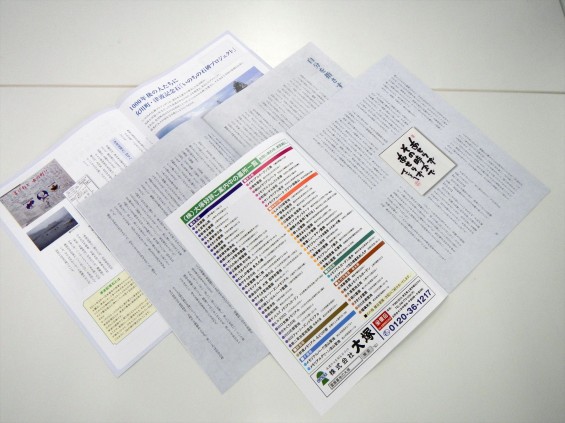2015年8月12日 水曜日 晴れ時々雨
こんにちは。埼玉県上尾市に本社を置き、首都圏にて霊園と墓地をご案内・ご紹介し、墓石の製造加工と墓所への据付施工工事という「お墓づくりのお手伝い」をしております石材店の株式会社大塚のブログ「霊園とお墓のはなし」です。
さてお盆(8月盆)です。
当社大塚は石材店ですので、お墓、墓石をご紹介しておりますが、お盆にお墓参りをするという方も多いかと思います。しかし今日の話題はお墓参りについてではありません。
お盆と言えば夏の風物詩として、盆踊りがあります。盆踊りというくらいですから、お盆時期に多く行われます。さてこの盆踊り、仏教の教えからスタートした習俗、お祭りと言われていますが実際はどうなのかちょっと調べてみました。


三省堂の新明解国語辞典によると
「ぼん おどり【盆踊(り)】盂蘭(ウラ)盆の夜に、あたりの住民が集まってする踊り。」
とあり、同じく三省堂の大辞林によると
「ぼん おどり【盆踊(り)】盂蘭盆(うらぼん)の前後に老若男女が多数集まっておどる踊り。年に一度この世に戻ってくる精霊を迎え,また送るための風習に発したもの。現在では信仰性は失われ,多くは娯楽的な踊りとなっている。 [季] 秋。」
とあります。「盂蘭盆」という言葉が出てきました。では今度はこの盂蘭盆を調べてみます。
「うらぼん【〈盂蘭〉盆】〔←盂蘭盆会ェ。「盂蘭は地獄でさかさまに ぶらさげられる苦しみを説く意」の梵語の音訳という〕(陰暦)7月15日を中心に行われる仏教の行事。いろいろの食べ物を盆に供えて、死者の冥福を祈るもの。ぼん。精霊会(ショウリョウエ)」
ということでした。やはり仏教行事のようですね。ちなみに「お盆」はというと
「ぼん【盆】一盛り付けを済ませた食器などを客の前に運ぶ、平たくて浅い道具(もとは、丸いものが普通だった。)二「盂蘭盆」の略。三盂蘭盆の時期である、中元。〔昔は七月十五日を指し、今は祭事を離れて七月中旬を指すことが多い〕「―暮れの付け届け」」 三省堂 新明解国語辞典
ということですので、盂蘭盆=お盆と考えて間違いないようです。
さて盂蘭盆は「地獄でさかさまにぶらさげられる苦しみを説く意」の梵語の音訳とあります。梵語ですのでサンスクリット語、インド発祥の思想になります。また、地獄というのは仏教でいうところの六道の一つ。お釈迦さまはこの六道の輪廻からの脱却(悟り)をめざしたわけですので、仏教よりも古い思想かもしれませんがわかりません。地獄という考え方は仏教よりも古そうです。
おそらく日本には仏教と共に地獄という考え方と一緒に盂蘭盆の習慣が伝わってきたのではないでしょうか。
ところが、もう少し角度を変えて調べてみると別のお話も出てきます。
ウィキペディアによると「お盆(おぼん)は、太陰太陽暦である和暦(天保暦など旧暦という)の7月15日を中心に日本で行なわれる、祖先の霊を祀る一連の行事。 日本古来の祖霊信仰と仏教が融合した行事である。」
日本古来の祖霊信仰と仏教が融合した行事、と書かれています。ウィキペディアは一般の方が編集し補完し合うサービスのため、正確性に欠く場合も多々あるのですが、確かに日本には仏教伝来以前より祖霊信仰がありました。間違いないかと思います。
またこのようにも書かれています。
「中華文化では道教を中心として旧暦の七月を「鬼月」とする慣習がある。旧暦の七月朔日に地獄の蓋が開き、七月十五日の中元節には地獄の蓋が閉じるという考え方は道教の影響を受けていると考えられる。台湾や香港、華南を中心に現在でも中元節は先祖崇拝の行事として盛大に祝われている。」
インドから仏教が伝わる途中に中華文化(中国)があります。中国ナイズされた情報になって日本に伝わったのかもしれませんし、情報の行き来は何度もあったはずですので複数の情報、後世になって中国から伝わったりなどの可能性も十分に考えられます。そして日本での状況はどうだったかというと
「盆の明確な起源は分かっていないが、1年に2度、初春と初秋の満月の日に祖先の霊が子孫のもとを訪れて交流する行事があった(1年が前半年と後半年の2年になっていた名残との説がある)が、初春のものが祖霊の年神として神格を強調されて正月の祭となり、初秋のものが盂蘭盆と習合して、仏教の行事として行なわれるようになったといわれている。日本では8世紀ごろには、夏に祖先供養を行うという風習が確立されたと考えられている。地方や、佛教の宗派により行事の形態は異なる。」
8世紀には確立、とあります。ということは当然それ以前からあったということ。日本への仏教の伝来は6世紀と言われています。
どうやらインド(ヒンドゥー教、仏教)、中国(道教)、日本(古来からの祖霊信仰)が混ざって日本で定着したものが「お盆」と思われます。


さて「盆踊り」。前述のとおり「お盆」はそれだけでも様々な行事の集合体のような日、期間だったようですが、そこにどうやって今のような「踊り」の要素が加わり発展したのでしょうか。
「盆踊りの世界」というサイト(http://www.bonodori.net/index.htm)があり、こちらを拝見したところ盆踊りが開花する下地として
①「風流」と「バサラ」・・・鎌倉時代(中世)に生れた「風流」と「バサラ」、永長の大田楽。
②融通念仏・・・仏教の合唱音楽である「声明」の大家「良忍」(ろうにん)を始祖とする「融通念仏」。「うた」「集団でうたう」という集団的パフォーマンスが注目(うたごえ運動)。
③踊り念仏・・・「念仏信仰」という宗教面と、「集団での踊り」という芸能、パフォーマンス面とを結びつけたもので、鎌倉時代の宗教家「一遍」が広めたことは広く知られています。
「踊り」という点で注目。※ただし、実際は空也系の踊り念仏を一遍が取り入れたと考えられている。
という以上三つの要素と段階が考えられるようです。
そして念仏がメインの「踊り念仏」から、踊りというパフォーマンスがメインの「念仏踊り」なるものに進化する地域が出てきました。当時の近畿の都市部(初見は奈良)に見られたようです。お盆の時期にも必ず行われていたという記録があるようです。この辺りが室町時代あたり(中世後期)。(「踊り念仏は、鎌倉時代には一遍上人が全国に広めたが、一遍や同行の尼僧らは念仏で救済される喜びに衣服もはだけ激しく踊り狂い、法悦境へと庶民を巻き込んで大ブームを引き起こした」ウィキペディア)
そして戦国時代には「風流」が大流行します。踊り念仏もより風流なものへと進化します。風流踊りが大ブレイク。
江戸時代初期頃には盆踊りが独自のものとして独立します。主役は町衆。江戸時代前期に盆踊りが最盛期を迎えるようです。(「江戸では7月に始まり連日踊り明かしながら10月にまで続いた。」ウィキペディア)


明治時代には「しばしば風紀を乱すとして警察の取締りの対象となった。」ようです(ウィキペディア)
そういえば、地元のお祭りの盆踊りも必ず警察の方がいたような記憶があります。
と、いうように盆踊りの歴史をたどってみましたが、確かに仏教と言えるでしょう。そして仏教だけでなくインド土着の思想や中国の道教、日本古来の祖霊信仰、そして日本で進化した風流や熱狂的なお祭りという側面があるということもわかりました(きっとそうですよね)
しかしながら、今となっては踊る人たちに細かい理屈は必要ないかもしれません。理屈はわからずとも、千年以上前から続く「お祭り」として感覚的に体感しているのが「盆踊り」なのかもしれませんね。