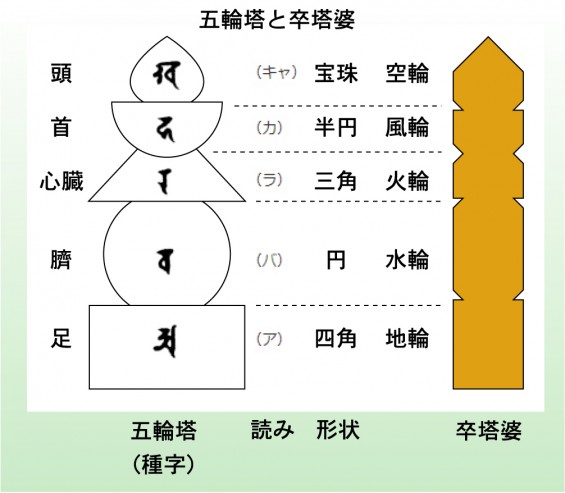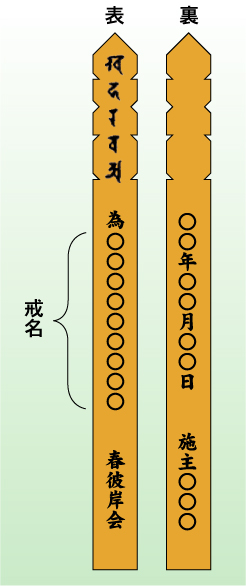2014年1月13日月曜日 晴れ
本日は成人の日です。成人されました皆様、ご成人おめでとうございます!
成人の日は、1999年までは1月15日に固定されていましたが、ハッピーマンデー制度が導入された2000年以降、1月の第2月曜日を成人の日とすることとなりました。
昨日、今日と、振袖姿の方や、紋付き袴の方など成人式に参加したであろう方々をちらほら見かけました。市町村によって、また地域によって式典の日付は前後しているようですが、関東ではおおむね12、13、14日のいずれかに成人式が行われているようです。
成人式は「冠婚葬祭」の冠にあたります。かつては、15歳で元服し稚児髷(ちごまげ)をおろし、冠をいただく式典でありました。
冠婚葬祭と言いますと、冠が成人式、婚が結婚式、葬は葬儀、祭は先祖供養を指しています。先祖をまつるの「祭り(祀り)」です。フェスティバルという意味の祭りはそこから発展していったものです。冠婚葬祭とは、その四文字で人生で起こる様々な出来事を指しており、現在ではそれぞれのシーンでの通過儀礼とも受け止められています。
株式会社大塚は石材店、墓石店ですので、この「先祖供養」という冠婚葬祭の祭りの部分で皆様のお手伝いをしております。
現代では、成人しますと例えばお酒を飲むことができるようになり、選挙権を手にすることができます。もちろん成人式は一年に一度の式典の日のことを指おり、飲酒にしても選挙権にしても法的には誕生日より起算されていますので、「飲酒解禁日」および「選挙権解禁日」が成人式というわけではありません。
成人式は一年に一度ある、人生一度きりの通過儀礼。しかしながら今日では、「過半の同級生が20歳をすぎての同窓会」「他の大人たちからの祝福を受ける式典の日」という側面が、いつのまにか意味合いのメインになってきました。これはいつくらいからなのでしょう。元服がなくなった明治からなのか、婚礼の時期が遅くなってきた昭和からなのか、戦後なのか。精神的に成熟した大人でなくとも、成人式はやってくるようになってきました。
冠婚葬祭の冠である成人式の意味合いが少しずつ変化してきているように、それぞれの四文字も時代とともに意味合いが推移してきています。
最近では資金ゼロでの婚礼(スマ婚)や、家族のみのお葬式(家族葬)やそもそもお葬式を上げない(直葬)など、「予算をかけないようになってきている」という大きな冠婚葬祭の流れがあります。これは良いこと良くないことと一言で言いきれるものではなく、世相や実情にあわせて変化してきているものと思います。
私たち石材店のかかわる「祭」にあたる先祖供養もその大きな流れの中で同じように変化してきているのが実情。最近ではお墓を建てないという方や、散骨にするという方法、変わったところでは宇宙葬といった供養方法もあるようで、様々なニーズにあわせた先祖供養、遺骨の行先となってきています。
ただし、遺骨の行先につきましては、多様な選択肢が増えてきているにもかかわらず、やはり大多数の方は昔ながらの「墓石を建てるお墓」や「お寺の納骨堂」というような形式での先祖供養に行きついているというのも実情です。「お墓はいらないからね」「散骨にしてね」という気持ちがあっても、いざとなると「やっぱりお墓はちゃんとあった方がいいよね」となるケースです。
それが残された方の希望(やっぱり手を合わせて会いに行ける場所がほしい)なのか、ご自身の亡くなった後の遺骨の行先についての考えの変更(残る家族のことを考えたらやはりお墓をつくっておこう)なのか、他のご親類の方からのアドバイスを受けてなのか、その複合なのか、理由は様々なのかもしれません。
が、時代とともに考え方が変わってきているのは事実です。
他の冠婚葬祭とともに、お墓についての考え方もこの先どんどん変わっていくのかもしれません。
ただ、ご先祖を大切に思う気持ちは何十年何百年とたっても変わらずにいてほしいな、と感じます。過去のご先祖様たちが大切に思い代々受け継いできたものは、可能であれば次世代に受け継いでいきたい。今を生きる私たちはご先祖様と子孫を考えたとき、リレーの一員として次の選手にバトンを渡すという使命があるのではないでしょうか。
成人式も結婚式も葬儀についても同様に、人生の中の大切なシーンについてじっくりと受け止める日であり続けてほしいものです。
石材店、墓石店の大塚としては、これからも「祭」の大切さを考えていきたいと思っております。