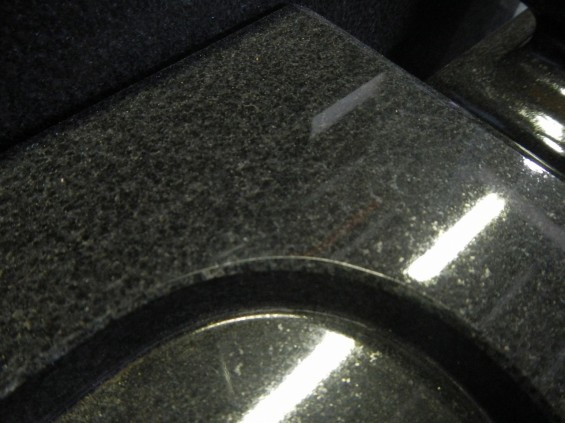お墓を建てると幸せになる? その3 家族・自分・故人の「シンボル」になります
前回「・お墓を建てると幸せになる? その2 心のもやもやを整理整頓できます。」に続いての第三回目です。
皆さんは、大河ドラマは見ていますでしょうか?現在放映している「軍師官兵衛」、視聴率はここ近年の大河ドラマ同様に奮ってはいないようなのですが、録画率といいますか、リアルタイムでは見ていないけれど録画して楽しむようにしている、という方はとっても多いようです。なので結果的にといいますか、だから故といいますか、大河ドラマファンの中ではとても評判のよい作品になっています。地デジで録画機能のあるデコーダーが普及して現代の日本で「視聴率」の数値的な信頼性はどうなのだろうか?(あまり意味はない?)・・・ということを先日の全優石セミナーで大河ドラマ税理士の山本先生に教わりました。と、視聴率の話はともかくとして、毎週楽しみにしており録画もばっちりして見させてもらってます。
そんな黒田官兵衛、過日の放送で、黒田家の家紋を新しく作り、家臣団に発表するというシーンがありました。旗に記された印は「藤巴」の紋。大河ドラマでのエピソードは次の通り。
信長麾下の有力武将で、官兵衛とも旧知の仲である荒木村重。信長の本願寺攻めの最中に荒木村重は、自身の拠点である有岡城に籠り毛利方に寝返ってしまいます。謀反です。明智光秀、羽柴秀吉による説得にも応じない村重。旧知の仲である官兵衛も説得に向かいました。ところが、村重は官兵衛にも「共に」と謀反を誘いますが、官兵衛は謀反に応じません。同心しない官兵衛を村重は有岡城の土牢に幽閉してしまいます。
その後、約一年にわたって村重は籠城。その間官兵衛は幽閉されたままです。土牢は劣悪な環境で、足を延ばすこともできず、常に湿り気もあり、毒虫もいるという状況でした。失いかけた気力の中、生死の境の官兵衛を励まし続けたのは、岩の間からほんの少しだけ見える外の様子と、少しずつ成長していく藤でした。徐々に成長していく藤はいつの日か花開きます。そんな藤をながめて心の支えとしました。
いつもでも帰ってこない官兵衛を、信長は「謀反の心あきらか」と断じ、官兵衛の唯一の息子で人質となっていた松寿丸(のちの黒田長政)の斬首を命じますが、竹中半兵衛の気転により松寿丸は隠されて生き永らえます。そしてついに織田勢により有岡城は落城となり、はじめて官兵衛が幽閉されていたことが判明。官兵衛は片足をひきずらないと歩けない状態でその後の半生を過ごすこととなってしまいました。生還後、この度の一連の経験により、「命を大切にする黒田家」とする、という意味で藤の花を家紋に定めました。
・・・そんなエピソードになっていました。(が、実際には官兵衛の旧主である小寺家の家紋が藤橘巴。おそらく小寺姓を下賜された際に紋も下されたのではないでしょうか)
官兵衛は、黒田家の家訓ともいえるような意味合いを込めて、藤の家紋を定めました。大きな辛い経験があればこその「シンボル」です。劇中では、家臣一同も当然納得の様子で、まさに「黒田と言えば藤の紋だ」と黒田家全体のシンボルになった瞬間でした。
ところが、現代のわれわれに置き換えてみると、「家紋」は確かにとても大切なシンボルではありますが「うちの家紋が何なのかわからない」という方や「なんとなく○○の紋だとはわかるが、正確には本家に確かめてみないと不安だ」という方も少なくありません。大切ではあるけれど、身近な「シンボル」だと言い切れる家も少なくなってきているようです。
今の時代では、官兵衛の時代の家紋に相当する「シンボル」は何になるのでしょう?
一つには「家」が挙げられるかもしれません。
「家」という字には日本ではいくつかの意味があります。一つは建物としての「イエ」。こちらは戸建ての住宅に限らず、集合住宅の一戸や、広めの土地のある場合は母屋や納屋、離れなども含めて指す場合もあります。またもう一つは「私の家族」という意味での「ウチ」。こちらは家族の場合だけではなく、親類縁者まで含める場合や、「私の所属するグループ」たとえば友人関係や学校や職場の仲間を指すような場合もあり「うちら」という言葉になるととても汎用性の高い言葉になります。
どのような集団でも、シンボルは必ずあると思います。ファミリーという意味での家族ならば、やはりわかりやすのは建物としての「家」。「住み慣れた我が家」という言葉や「夢のマイホーム」という言葉があらわすように、人の一生の中でもとても大きな、シンボリックな存在なのは確かです。「おうちへ帰ろう」の場合の「うち」も建物含めてファミリーのいる場所という意味なので、同じ使い方ですね。
ところが、建物としての家を永続させるのは、現代では少し困難な場合もあります。転勤などによる引越し、建物が古くなったり手狭になったりした場合には建て直したり。昔は住居の寿命はとても長いもので、現代にも残るような民家は何百年と生き続けていますが、残念ながら現代の住居の寿命は「何百年」というわけにはなかなかいきません。木造であっても、鉄筋コンクリートであっても同様でしょう。とても残念なことですが、建物としての家は、シンボルでありつづけるには限界があるのも事実です。
また一つには「家業」もシンボルと言えると思います。
子や孫に受け継がれる店や、会社、代々続く集落での役割なども家業と言えるでしょう。日本は世界的にも稀な、長寿企業の育つ国柄と風土があります。1000年続く家業は、もはや伝説のような企業しかありませんが、いわゆる「老舗」と呼ばれている店や企業、老舗とまではいかずとも、お祖父さんから受け継いだ店、お父さんから受け継いだ店、というものを継続されているという方は少なくありません。しかしながら、家業を継ぎ、継続させて次世代に渡すというのは並大抵のことではありません。生半可な気持ちではなかなか難しいものです。だからそこ受け継いできた方々にとっては「シンボル」と胸を張って言えるのではないでしょうか?
ただ、家業を維持することができている方々はほんの一握り。今現在は受け継ぐことができていても、それを次の世代に無事にトスすることができるのか・・・。今現在おおいに悩まれているという方もたくさんいらっしゃることと思います。
また、「家業は我が家のシンボルだ」と言えるのは、血のつながった人々とさらにその方々と婚姻関係にある方々に絞られます。オーナー一族とも言い換えられるでしょう。長年勤続されたという方がいたとしても、その方にとっては「家業」ではありません。勤め人の方にとっては、あくまで勤め先であって、自分の家のシンボルとするのは少し難しいものと思います。
故郷自体がシンボル。という考え方もあります。
ふるさとと言う言葉には、実に様々な思いと時間と思い出とを詰め込むことができます。ただし、故郷をシンボル的に感じることができる人々というのは時間的な制約があります。その土地で生活をした人でないと、その土地で生まれたりした人でないと、シンボルとして土地を指すことはできません。10年20年と経つうちに、次世代の子供たちが生まれた場合には「家族みんなのシンボル」という意味から少しずつずれが発生してきてしまいます。ただし、そこは家長なり年長者が「うちは昔あの故郷で苦労しながら家を守ってきたんだよ」と次世代に伝えていくことは可能かと思います。子供たちはきっとシンパシーをもってその土地を憧れることと思います。しかし、やはりどうしても時間の経過とともに意味合いが薄れて行ってしまうのは仕方のないことかもしれませんね。
そこで、家族のシンボルとして、「お墓」を位置づけるというのはいかがでしょう?
この記事を書いています、ブログ担当のTのお墓は、あまり古くはなく、建ててから40年弱しか経っていません。しかし、私のイメージとしては「お墓=親戚が集まる場所」のような印象を持っています。幼少期、親戚のおじさんやおばさん、また、従妹たちとピクニックのような気分で出かけた記憶があるからかと思います。幸いマイナスイメージはありません。お墓と言うと、幽霊やおばけ、怖い、じめじめしている、悪い気がある、縁起が悪いなど、どうしてもマイナスイメージを思い浮かべるという方もいますが、最近のお墓は、だいぶちがってきています。お墓を買う人も現代の日本人です。現代日本人が「こういうお墓ならほしいなぁ」というお墓が実際に増えてきています。明るい環境や足元の良さ、使い勝手の良さなど、日本人らしいカイゼンがなされている墓地も少なくなく、昔ながらの寺院墓地であっても明るい雰囲気の墓苑になっていたりしているところも少なくありません。
私の友人に「あらい」という名前の人がいるのですが、彼の家はいつも笑いの絶えない家庭。なのでお墓を建てるとき、墓石に○○家と刻むところを、自身の苗字にひっかけて「笑い」と刻んだそうです。しかも笑という文字を、まるで人が笑っている絵のようにカタチを崩して彫刻しました。私は「あーなんて彼の家らしい、シンボリックなお墓なんだろう」と思いました。友人はお父さんに「(笑)にしよう」と言ったそうですが、さすがに「かっこ笑い」は却下されたそうです(笑)
また別の友人の家のお墓は、その家に縁のある故郷の有名な山(高千穂)をお墓に刻みました。お墓参りをすると眠っているお父さんのみならず、その家のルーツをその都度思い出すことができるようになっています。
またある人は故人の好きだった色の石材を使用してデザインしたお墓にしたり、故人の職業にあわせたデザインの墓石にする人もいますし、故人の趣味である音楽の楽譜や、囲碁の白黒の石の刻まれた盤面、家族に向けてのメッセージや、家族だけでなくお参りに来た人に語りかける言葉を刻んでいる方もいます。
前述しました我が家のお墓の場合、たくさんいる従兄弟たちから「お墓に家紋が彫ってあるから、家紋を自然と覚えたよね!」と言われました。いまその墓石に刻んである家紋を、生まれて間もない従兄弟の子供たちも眺めていることと思いますので、自然と覚えていくのではないでしょうか。
現代のお墓には、どんなシンボルにするのか、無限の可能性があるともいえるのです。
沢山ある可能性の中から、さまざまな選択肢の中から、自分たちの家族らしい、自分らしい、故人らしいシンボルを定めることができるのです。幸いなことに、墓石は数百年と残すことのできる媒体です。もちろん世代が変わって「シンボル」としての意味合いが薄れていく可能性はありますが、後々の血縁者が「あー、ご先祖様はこんなことを考えていたんだな」ということを伝えることは十分に可能ですし、お参りのたびに語りかけることもできる「タイムカプセルや、タイムマシンにもなりえる施設」ともいえると思うのです。
お墓を建てると幸せになります!家族や自分、故人のシンボルとして、家族のつながりやメッセージを伝え残すことができるからです。
と、考えますがみなさんはいかがでしょうか?
・・・「戸籍」も地味ながらシンボルともいえるなぁ、と最後に思い出してしまいました。